�M�B�ɊW����{�͂�͂�悭�ڂɂ��A�}���قŎ��Ȃǂ��ēǂދ@�������
���������i����o�g�̍�ƁA(���j�����s�m���j
�E�u�ӂ邳�Ƃ�n�����j�v�i���{�����o�ŋ���A1990/6�j
���w�Z���́u�̋��i�ӂ邳�Ɓj�v�A�u�O����i���ڂ����j�v�A�u�g�t�i���݂��j�v�A�u�t�̏���v�A�u�t�������v�Ȃǂ悭�m��ꂽ���̂��쎌��������C�V�i�����̂��䂫�j�̕���B����́A���쌧�i���j����s�o�g�A����t�͑��A�юR���w�Z���t�Ř@�؎��i�����́u�j��v�̕���ƂȂ����j�̖��ƌ����B
�E�u�~�J�h�̏ё��v�i���w�فA1986/12�j
�����O���[�v�̑n�Ǝҁ@��N���Y���y�n����肵�A�v�����X�z�e���������Ă������ꂪ�`����Ă���B�y���̐�P��v�����X�z�e�������̈�B
�@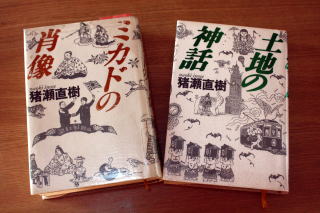
��N���Y�E�����ɂ��Ă�, �y���̊J���҂ł�����A
�E �u���������|���̉��Ɖe�v �������O�Y�i�T���f�[�ЁA2004/12�V���P�Łj���ǂB
�O��
�E �҈�@���i�����@�������j�i�҈�@���͒� ����̃y���l�[���j���u���̏ё��v���ǂ�ł���B
���蓡���i�M�B�ؑ]�E�n�U�i���j�����Ð�s�o�g�j
����32�N(1899)�|38�N(1905)�����`�m�̋��t�Ƃ��ď����ʼn߂������B�j
�E�u���ʉ�Ɓv(���蓡���S�Z�ҏW�P)�i���y�o�ŎЁA2003/4�j
�ێR�Ӊ��i�܂��܁@�j�����f���B�ێR�Ӊ��́A���쌧�i���j����s�I�Ái�˂j�o�g�̉�ƁB�ێR�Ӊ��L�O�ق�����s������ٓ��ɂ���A���̍�i��W�����Ă���B
�@
�E �u�M�B�䂩��̔��p�Ƃƕ��i��|�w�|���������Ȃ��n��̗�����|�v�ݓc�b���i���쌧�M�Z���p�يw�|���j�i�ق��������ЁA2012/7�j�ێR�Ӊ��A���R�h�O�A���c���A���R�@�A�ȂNjL�q�B
�E �u���{�̍�ƕS�l ���蓡���\�@�l�ƕ��w�v ���R��q�i�א��o�ŁA2004/4�j
�E �u�w�j��x�̖q��Ɣ�b�v ���@���i�ق��������ЁA1994/10�j�A�u���蓡���Ə����@�_�Ö҂̗F����߂������v�i��Ȑ앶�ɁA1900/7)
�E �u�ԕǂ̉Ɓv(�������) ���V�m�O�i�ق��������ЁA1900/11�j
��[�N���i���{�l���̃m�[�x�����w��܁i���a43�N(1968)�j
�y���ɕʑ��������Ă���A�y���E�M�B��ɕ`���ꂽ�����̂����A�������ǂB
�E�u�����v�i��[�N���S�W�@��Z���j�i�V���ЁA1981/4�j
�א��݁A�O�c���݂̕ʑ���K�˂�V�[�����`����Ă���B
�E�u�q�́v�i����j�A
�E�u�S�����搶�v�i����j
�@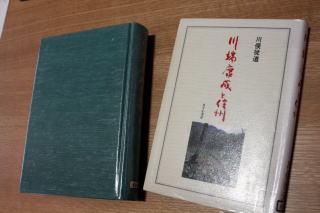
�E�u��[�N���ƐM�B�v �얓�]���i����܂��@���݂��j�i���������[�A1996/11�j
�R�����F��[�N���͏��a12�N(1937)8���A�y�����m��1307�̕ʑ����O���l�鋳�t����w���A11�����ɐ�[�v�Ȃ��ʑ��������g�������ƁA�Ǖ��E�������Ύ��ŏĂ��o���ꂽ�x�C�Y����ĕ�炵���B����12�����ɂ��̕ʑ��Ŗx�C�Y�́u�������ʁv�̏I�́u���̂����̒J�v��E�e�����Ƃ����B
���퐶�q
���L��Y�E�퐶�q�v�Ȃ́A�k�y���̖@����w���̎R���ʼnĂ��߂������B�퐶�q�͏I�������̎R���Ŏ��M�����𑱂��A99�܂Ō����������Ƃ̂��ƁB�R���̗���h�S���R�[�h�i���������j�͌y������ɂɈڐ݂���Ă���B
�E�u���M�@�S���R�[�L�v�i��g���X�A1964/8�j�@���a30�N�ケ��̐��M�A��ԎR�̕�������B
�E�u�]�`�@���퐶�q�[���H���ĐX�ցv �⋴�M�}�i�V���ЁA2011/9�j
 ���̂R�D�y���̕����{��(2)�|�y������� ���̂R�D�y���̕����{��(2)�|�y�������
�y���䂩��̕��w���Љ��y����M�B�̏Љ�I�Ȃ��̂��ǂB
�E�u�V�E�y��w�U���\���w�҂����̌y���v(�㊪) �g���T���i�y���V���ЁA2009/3�j
�E�u�y��w�U���@����V�Łv ����M�ہi�y���ό�����A1968/8�A2000/8 12�Łj
�E�u�y����ޓ��L�v �L�쏬��q�i�y���V���ЁA2010/8�j
�E�u�y���鋫�T���v �y��B�l�b�g�i�y���V���ЁA1999/4, 2008/8 2���j
�E�u�M�B�~�X�e���[�I�s�v �ǔ��V���В���x�ǁi�ق��������ЁA2012/8�j
�E�u�Y���ꂽ�y���l�v ���V �A�i2016.02�j
�E�u�u�R���������@�y���Ƃ��̎��Ӂv �ےJ �Z�Y�i�n�p�ЁA 2016/12)
�E�u�Ђ��Ƃ���y���v �R�� �m�q�i���|�t�H�A2002/.7)
�@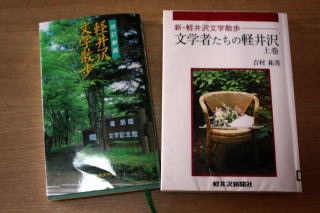
������(�z�K�o�g�j
�R�x�����ŐV�c���Y��ǂ�ł�����A�����Ă������̕v�l�ŁA�������z�K�̏o�g�ł��邱�Ƃ�m��A����
�E�u����鐯�͐����Ă���v(�������ɁA1976, 2008/7����12��)
��ǂB�̌������Ƃɂ������B������������̊����I�ȕ���i�Ō�ɐz�K�ɂ��ǂ蒅���j�B
�@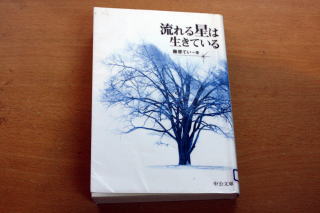 �@ �@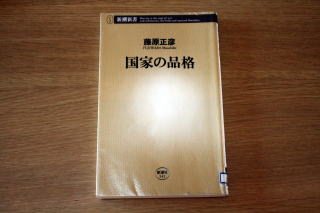
�������F
�����Ă�����̎��j�i�u����鐯�͐����Ă���v�̒��ŁA�Q�łĂ�����ɘA����Ė��B����- �j�ŁA���w�Ґ��F���̃G�b�Z�C���������ǂB���{�l�̍l�����E�s���K�͂̂悤�Ȃ��Ɓi���ݕ��f����NHK��̓h���}�u���d�̍��v�ɂ��ʂ���j���A�����ɏq�ׂ��Ă��ċC�������ǂ��B���݁@�u�T���V���v�A�ڂ́u�nj��ό�v���ǂ�ł���B
�E�u���Ƃ̕i�i�v(�V���V���A2005/11, 2006/4 22��)�A�u���̍��̂����߁v�i���|�t�H�A2006/4)�A�u�nj��ό��i����������j �傢�Ȃ�Ë��v�i�V���ЁA2010/11�j�A�u�nj��ό� �n���ɍ���l�v�i�V���ЁA2011/10�j�A�u�nj��ό� �ڋ����f�����v�i�V���ЁA2013/3�j�A
�E�u�������F�@���q�̂Ԃ����j�U���v�i���|�t�H�A2012/3)�A
�E�u�ǏD�@�T�E�_�[�f�v(���|�t�H�A2012/11)�i���E�V�c���Y�����M�A�S���Ȃ�����32�N�����Ă��̌㔼�����������������B�����E�吳�����{�������A�Ō㓿���ŖS���Ȃ�A�|���g�K���O�����������X�̕���)
���Ɛm�V�i�܂����@�܂����j�u�ΎR�̂ӂ��ƂŁv(�V���ЁA2012/9)(���z�v�������ɓ��������Ⴂ���z�Ƃ���ԎR�[�ɂ���ẲƂŌ��z�R���y�̐v�������镨��B���z�v�ƂȂǂ̃��f����z��������A��ԎR�E�y�����ӂ͋�̓I�ɐ����o�����肵�ċ����[�������j
���c�����u�敶�W�@�Ԃ̐��p�i�C���ЁA1983/12���ŁA2004/5 4�Łj�i���c�ɔ_��������Ă���ꂽ���҂��A��̉ԂJ�ɕ`���Ă���j
�@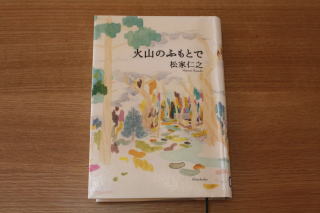 �@ �@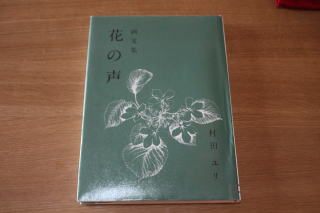
�g�����O�u���z�Ƌg�����O�̂��ƂP�O�O�@���z�͎��v�i�����ЁA2005/10�j(A.���[�����h�Ɏt�������g�����O�̕ʑ��u�����ȐX�̉Ɓv�͌y���ɂ���B�e�c���p�ق̒���ɂ���e�c�a�̃A�g���G���g�����O�v�j�A
�����D���u�H���Q��V�ԁ@������炵�v(PHP�������A2013/4)�i���c��LEMM HUT�Ƃ��鏬��(�R��)�j�A�u���ʂ̏Z��A���ʂ̕ʑ��v(TOTO�o�ŁA2010/5)
��c���Y�u��H�������v�i��A���j(�������_�ЁA2013/2)((�]�˖����A�Q�Ό��Œ��R�����]�˂܂ŁA������d��Ⴋ�����h��H�h�i���O�j�B���z�K�E�⑺�c�E�y���h�E�O�X���Ȃǒm���Ă��鏊��A�����˂̉����i�Ƃ������A�}���\���j�����S���̂��P�l�̍s����o�Ă�����Ŗʔ����j
�X������u�����̏ؖ��v(�������_�V�ЁA2004/8)(�k�A���v�X�䍂�A��ł̑����)
�R�{�Δ��u���T�씞���@���鐻���H�����j�v(�p�앶�ɁA1977/4, 2008/9 58��)(�씞�����z���Ĕ�ˁi���j����M�Z�i���{�E���J�j��)
���A���[�E�t���C�U�[�u�p�����g�v�l�̌����������{�v �q���[�E�R�[�^�c�B�i�ҁj�@���R�r�v�i��j(�W���ЁA1988/3)
�p�����g�q���[�E�t���C�U�[�͖���23�N���y���ɏ��߂Ă̗m���ʑ������݁B�v�̎���A�������v�l����������̓��{�̗l�q�������h���ŏo�ŁB�y���̕ʑ��u���a�̋{�a�`�ڊo�߂���ԁA��������ԁv����R���E�a�����A�����E�z���ω��Ȃǂ��o�Ă���B�i�ʑ��͖Ŏ��j
���a ���j�u�ኄ���v(�^���ˏo�ŁA2018/3)
 �M�B�̖{(4)�i2016�N9���j �M�B�̖{(4)�i2016�N9���j
 �M�B�̖{(2)�i2010�N1���|2���j+ �M�B�̖{(2)�i2010�N1���|2���j+
 �M�B�̖{�i2009�N2���|8���j+ �M�B�̖{�i2009�N2���|8���j+ |
|
![]()