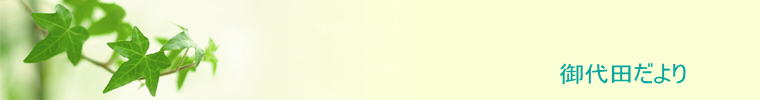
●真楽寺(2008年8月)
浅間山の噴火が鎮まるよう祈願のため、用明元年586年に開山したという。(浅間の別当寺として、上州側の延命寺と二つあったが、延命寺は天明の噴火(1783)で消滅し、信州側の真楽寺だけ残っている。)
毎年7月の御代田・龍神まつりは、この真楽寺での開眼式と龍神の舞いから始まる。
(1) 真楽寺仁王門。(門内にある金剛力士像は室町時代1395年の紀年銘)
右側に阿形(口を「あ」とあけ)、左側に吽形(口を「うん」と結び)の仁王像が「阿吽(あうん)の呼吸」で寺を守っている。
(2) 大沼池には龍がいる。(龍神まつりでは龍がお清め儀式でこの大沼池に飛び込む。)
(3) 石段と厄除け観音・真楽寺観音堂(江戸時代1665年建立)
石段手前に六地蔵が並んでいる。(石段の数は67段。小学生が数えていた。) 観音堂周囲には唐獅子、象、龍の彫刻。
(4) 境内に芭蕉句碑「むすぶよりはや歯にしみる清水かな」(このあたりは浅間山のきれいな湧き水がある。大沼池もこの湧き水である。)
(5) 樹齢1000余年という神代杉
(6) 三重の塔(江戸時代1613年消失のあと1751年再建)
高さ21mは長野県で最も高いという。周囲に龍、麒麟、タンポポ、ミズバショウの彫刻。
(7) 真楽寺の本堂
(8) 境内にある牛頭観世音(馬頭観音はよく見るが、牛は珍しい。鍾乳洞のように水が滴り落ち、乳首が5本ある。)
(9) 頼朝公の逆さ梅、弁慶の腰掛けの松。
(10) やまゆりがきれいに咲いていた。(やまゆりは御代田の町花)
境内の西側には日本一大きいという子育地蔵菩薩(高さ20m)も建っている。
(1) 真楽寺仁王門 |
(2) 大沼池には龍 |
(3) 石段と厄除け観音・真楽寺観音堂 |
(3) 厄除け観音・真楽寺観音堂 |
(3) 厄除け観音・真楽寺観音堂 |
(4) 境内に芭蕉句碑 |
(5) 樹齢1000余年という神代杉 |
(6) 三重の塔 |
(6) 三重の塔 |
(7) 真楽寺の本堂 |
(8) 牛頭観世音 |
(8) 牛頭観世音 |
(9) 頼朝公の逆さ梅 |
(9)弁慶の腰掛けの松 |
(10) やまゆり |
![]() その2.真楽寺:大沼の池の湧水
その2.真楽寺:大沼の池の湧水
![]() 浅間八景
浅間八景
![]() 御代田の龍神まつり
御代田の龍神まつり
![]() その1. 寺院(2009年3月-4月)
その1. 寺院(2009年3月-4月)
![]()