今年のNHK大河ドラマ「八重の桜」は、会津出身で江戸時代幕末から明治・大正・昭和まで生きた新島(山本)八重の物語である。会津藩砲術指南役の家に生まれ、戊辰戦争・会津城で鉄砲をとり最後まで戦った八重、明治になって京都で新島 襄(にいじまじょう)と出会い結婚、同志社大学の創設に関わる。
新島 襄は、上州(群馬県)の安中藩の江戸屋敷詰め祐筆の家に生まれ、蘭学・洋学を学び、オランダの軍艦を見て幕府の海軍伝習所に入り、尊王攘夷の中、密航 箱館(函館)からアメリカ商船に乗り込み出国(喜望峰を回ってボストンへ)。明治になりクリスチャンとして帰国、キリスト教の同志社(のちに大学)を創設する。
新島襄は、上4人の娘(姉)のあと5番目に男子誕生し、祖父が “しめた!”と喜んで、七五三太(しめた)と命名したという(しめ縄のことを、藁を七本・五本・三本垂らして結ぶので七五三縄(しめなわ)とも書く)。襄(じょう)は出国の船の船長から、ジョー(ジョセフ)と名付けられた。
戦後設立された新島学園は群馬県安中市にある。新島襄が浅間山(に寄せて自分の熱情)を詠んだ歌「朝な朝な山に煙の絶えざれば 山の心根いかにあるらん」
八重ブームで多くの本が出ており、いくつか読んだ。「ならぬことはならぬのです」の八重の会津精神や、幕末から明治にわたる変革期の日本人の躍動する生き方、上州・安中出身の新島 襄 にも興味を覚えた。
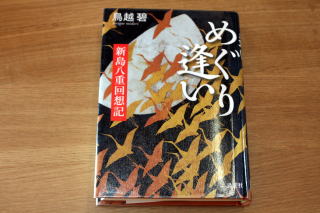 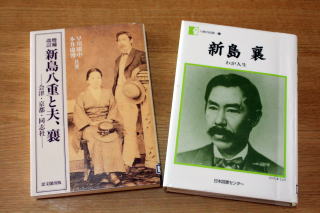
・「めぐり逢い 新島八重回想記」鳥越 碧(とりごえ みどり)(講談社、2012/11)
・「新島八重 おんなの戦い」福本 武久(角川書店、2012/8)
・「増補改訂 新島八重と夫、襄−会津・京都・同志社」早川廣中・本井康博(恩文閣出版、2011/12)
・新島 襄「わが人生」(日本図書センター、2004/8) |
|
![]()