|
・串田孫一・今井道子・今福龍太編「浅間山(日本の名山)」(博品社、1997/10)
浅間山を舞台にした詩歌・エッセイ・小説集。
アーネスト・サトウ、寺田寅彦、正宗白鳥など多くの人が浅間山登山について書いている。軽井沢滞在の多くが登山している。
物理学者で随筆家の寺田寅彦は、この本の随筆では浅間山の登山プランを空想するだけで実際には登っていないようである。別の随筆「小浅間」では『小浅間への登りは思いのほか楽ではあったが、
- -』と小浅間登山を記している。
なお、この本の深田久弥「浅間山」は、「日本百名山」の浅間山と同じである。
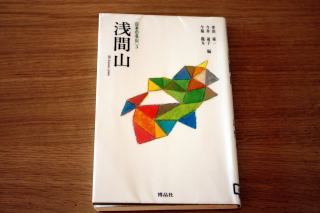
|
作者 |
| 詩歌の浅間 |
若山牧水、尾上柴舟、土屋文明、前田普羅、島崎藤村「小諸なる古城のほとり」、北原白秋「落葉松」、谷川俊太郎 |
| 浅間讃 |
後藤明生「浅間五景」、柴田南雄、水上瀧太郎、宇佐美英治、 |
| 浅間山考 |
志賀重昴、高頭式・編、深田久弥「浅間山」 |
| 四季折々の山 |
佐藤春夫「浅間の四季」、堀 辰夫「初秋の浅間」、小島烏水 |
| 浅間山登山 |
アーネスト・サトウ「恐怖の活火山 浅間山に登る」、大町桂月、志村烏嶺、土居通彦、寺田寅彦「浅間越え」、正宗白鳥「浅間登山記」、細貝 栄、石井昭子、田淵行男 |
| 浅間山麓だより |
田部重治「浅間追分高原」、谷川哲三、茨木猪之吉、岸田衿子「浅間六里ケ原」、福永武彦 |
| 火の山浅間焼け |
辻村太郎、伊藤和明、萩原 進 |
浅間がよく見える場所の記述がいくつかあり面白い。
佐藤春夫は御代田の南方小一里の地点(平根)に居たようで、『車窓の浅間は平原と御代田あたりの中間で、秋、蕎麦の花ざかりの頃が一番いい - - 』、また『浅間を見るにはここ平根が絶好の位置 - - 』としている。
後藤明生は追分で暮らしたが、特に気に入った場所を五つ見つけ「五大浅間」と名づけている。
それぞれ自分が住んでいるところから見る浅間を絶景と言っているようだ。(御代田の「浅間八景」を歩いたように、後藤明生のいう追分の「浅間五景」を一度たどってみたいと思っている。)
 追分の浅間五景(2010年3月) 追分の浅間五景(2010年3月)
・岸田衿子(えりこ)・岸田今日子(きょうこ)「ふたりの山小屋だより」(文春文庫、2001/8)
群馬県の六里ヶ原の”山小屋“(北軽井沢(法政)大学村)で過ごした岸田国士(きしだ くにお、明治23年(1890)-昭和29年(1954))の長女・次女たちのエッセイ。草軽電鉄や六里ヶ原の情景、文化人(野上弥生子など)との交流の話が興味深い。
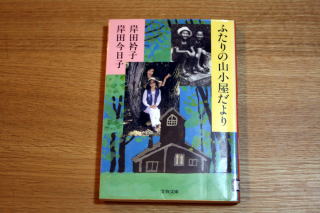
・古越 百(ふるこし はげむ)「浅間山物語」(ほおずき書籍、2005/8)
地元御代田町在住の著者による浅間山にまつわる物語。御代田から直接浅間山へ登る話も出ていて興味深い。御代田口という御代田(塩野)からの直接登山ルートがあったようだ。
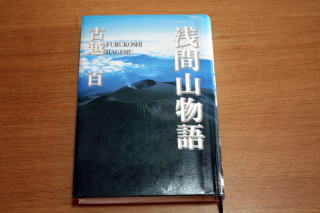
・ 後藤明生(めいせい)「笑坂」(筑摩書房、1977/5)、
追分の別荘での短編随筆集で、道、笑坂、屋根、不思議な水曜日、煙突、ひと廻り、石尊行、女街道、離れ山、分去れ、を含む。「笑坂(わらいざか)」は中山道の分去れ(わかされ)から御代田方向へ下るところあたりを指すようで、追分の「中山道69次資料館」前に『ここは中山道
笑坂 浅間山麓の坂道を上って来た旅人が追分宿の燈火を見て笑みをこぼした所』と説明がある。
 笑坂の説明(「中山道69次資料館」前) 笑坂の説明(「中山道69次資料館」前)
「ひと廻り」のなかに兼好法師の「寸陰を惜しむ人なし」の引用があり、『食事、排便、会話、歩行』は生きるための止むを得ない要件と記している。ウォーキングが兼好法師の時代から不可欠の要件と考えられていることに、なるほどと感心した。後藤明生もよく散歩していたようだ。(あとで徒然草を見たら、第108段に『一日のうちに、飲食(おんじき)、便利、睡眠、言語(ごんご)、行歩(ぎょうぶ)、やむ事をえず-
- 』と、睡眠も含まれていて、安心した。(「徒然草」(今泉忠義 訳注)(角川文庫、2009/5)による))
|
![]()